みかん・カンキツのドローン散布の今を考える
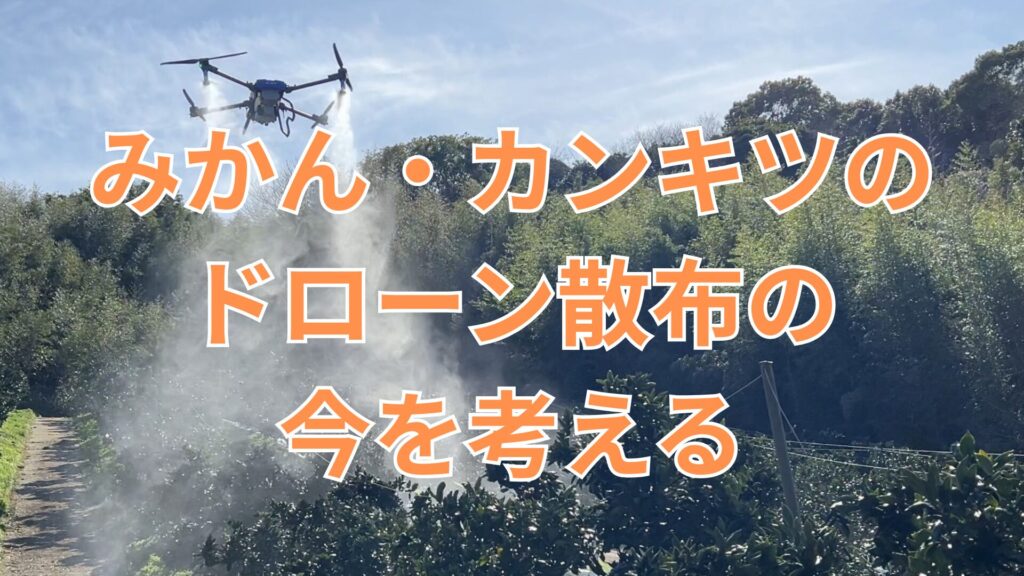
皆さんこんにちは。
AIやロボットなど発展めざましい昨今ですが、農業において最新技術の一つであるドローンを導入する方が増えてきました。そんな中でも、まだまだ導入をためらっておられる農家が多い果樹分野において、主にみかん・かんきつ栽培の分野で、今後のドローン普及について考えてみました。
果樹農業におけるドローン活用の可能性
果樹農家の減少が止まりません。その主な原因は、なかなか単価が上がらず、収益が少なかったこと。そして、植え付けしてから収入になるまでの期間が長すぎることだと思います。それと同時に、傾斜や段々畑が多い中で、作業労力が大きいことも、その大きな原因と考えられます。
年間の作業の中でも、時間と労力の掛かる作業が防除です。みかん、かんきつについて言えば、なかなか無農薬や減農薬(特別栽培農産物)へチャレンジするハードルは高いものです。農薬なしでは、外観はかなり悪くなりやすいからです。やはり、月に最低でも1回は防除する方がほとんどだと思います。
みかん、かんきつ栽培においては、防除に時間が掛かると言うだけではありません。夏の猛暑の中、ゴーグル、マスク、カッパを着用し、広い面積を重たいホースを引っ張りながらの作業は、過酷と言う以外にありません。またスピードスプレイヤー(SS)での散布は、効率的で肉体的負担も小さいですが、薬液をびっしょり体にかぶりながらの作業に、耐えられないという方も多くいらっしゃいます。さらには、傾斜地での作業のなか、スピードスプレイヤーが転落、横転し、命を犠牲にされた方も少なくありません。文字通り「命を削って防除している」というのが、みかん・かんきつ農家の現状ではないでしょうか。
そんな中で、やはり期待されているのがドローンによる防除です。
ドローンにる防除のメリットは大きすぎます。
・防除作業時間は、SSと比べて1/5程度、手散布に比べると1/20程度になる。
・適期散布を実現できる。
・肉体的負担、薬剤被曝、命の危険が極めて少ない。
・使用水量が少ない。
・散布技術の差が少ない。また、園主がケガや病気でも防除作業を他人(業者)に任せられる。
・小面積圃場でも、それほど効率が落ちない。
・面積当りの植栽密度が増える。(SS用の園地に比べて)
・基盤整備や園地改造の必要が少ない。
もちろん、デメリットもありますが、今後みかん・かんきつ栽培にドローンを導入するメリットは非常に大きいということは明白です。
ドローンの導入についてのメリットやデメリット、機種の選定や注意点については、以前書いたブログにも詳しく書いております。ぜひこちらをご参照ください。
果樹用ドローンの検討と導入について!
みかん・かんきつに適用のあるドローン対応の農薬一覧
多くのみかん・かんきつ農家がドローン導入に足踏みしてしまう原因の一つは、使用出来る薬剤が少ない。ということです。
確かに、手散布やSSで散布できる農薬に比べると少ないですが、私が調べたところによると現在22種の薬剤が、ドローンでの散布が可能となっています。かなり登録が増えており、実用的なレベルに到達していると思います。
以下に、現在の調査によるドローン対応農薬の一覧を掲載します。
ドローン(無人航空機による散布)の登録がある農薬(2025.10.1現在)
この資料は、著作権フリーとしますので、関係者はご自由にお使いください。ただし、ご利用に当たっては必ず最新情報をご自身でお確かめください。また、定期的に最新情報に更新したいと思いますので、シェアする場合はこのページへのリンクの形でご紹介ください。間違いや最新情報がありましたら、ぜひお知らせください。
それから、各農薬の散布時期については、私の調査と経験に基づきリスト化しました。液肥等も記載がありますが、使用されない方は無視してください。ただしこちらも、利用はあくまでも自己責任でお願いいたします。状況によりご自身で、アレンジした方が良いかと思います。また、よりよいアドバイスがありましたら、ぜひご連絡ください。こういう事は、みんなで技術共有するのが良いと思います。
ドローンによる農薬散布時の注意点と問題提起
ドローンによる農薬散布における注意点は、まず安全面です。これは機種選定をしっかりすること、習熟するまで練習を重ねること、そして基本を守ることです。
たとえば、飛行中のドローンの進行方向に立たない、また10m以内に接近しない、というのは本当に基本的な注意事項です。果樹用のドローンは、基本的にかなり大きな機体となります。非常に大きなプロペラが回りながら自分の方に飛んで来たときの恐怖は、身動きができなくなるほどです。常にドローンの動き、障害物に目を凝らし、万が一自分に向かってきたときは、咄嗟に身を隠せるよう何かの後ろに立っていた方が安全です。もしも当たったときは、国土交通省案件の重大事故(航空機事故)となりますので、決して過信せずに安全確保の体勢で防除することが非常に重要です。
また、園地には、最低限の整備が必要です。ドローンが着陸、飛行するための安全を確保する必要があります。離着陸スペースや、防風垣・隣接樹木の整備が必要となります。ドローンの事故や故障のほとんどは、何らかの障害物に当たることで発生します。
さらには、農薬そのものの使用制限に注意する必要があります。農業者が、農薬を使用する場合は、農薬取締法に規定される「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」に準拠する必要があります。
農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令
https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_kaisei/h141211/h141211f.html
この法令に違反した場合は、青果物の出荷停止や、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金という事態を招くことが考えられます。知らなかったでは済まされないため、十分に注意する必要があります。
「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」のざっくり解説
では、「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」には何が書いてあるのか。いちいち法令を熟読する方は、ほとんどいないと思いますので、私が読み砕いて、解説いたしましょう。(私は熟読し、疑問点、問題点を農水省および環境省に問い合わせました!笑)
この法令、非常に簡単に、ドローン防除に関する点だけを抜粋すると以下のようにまとめられます。
・対象作物の適用(登録)がある農薬を使用すること。
・農薬ラベルに記載のある量を超えて散布しないこと。
・農薬ラベルに記載のある希釈倍数より低く(濃く)して散布しないこと。
・使用時期や使用方法(散布方法)、使用回数制限を守ること。
つまり、一言で言えば「ラベルに書いてあることを守れよ!」ということです。
さて、ここで問題ですが、ラベルに記載のある希釈倍数より高く(つまり薄く)使用することは、禁止されているのでしょうか。また、薬液の量をより少なくして散布することは、禁止されているのでしょうか。つまり、農薬を基準より少なく使うことに問題はあるのか?という質問です。
この点について、疑問がありましたので農水省、および環境省に問い合わせましたところ、その返答はつまり「禁止されてはいないが、ラベルの使用方法を遵守してください。」でした。いかにも、お役所らしい返答ですね。ちなみに、その理由を尋ねたところ、「農薬の使用量が少ないと、病害虫の薬剤抵抗性の獲得を助長してしまうかも知れない。」ということを言っていました。え、と思って、いろいろと突っ込みたくなりましたが、自重いたしました。(笑)
しかし、つまり「薄く」散布する事や、「少なく」散布する事は、法的に禁止されていないと解釈されます。この点は、私は重要だと思っています。
例えば、デランフロアブルのドローン散布による適用は、20倍希釈となっていますが、これを40倍希釈で散布することは法律違反ではありません。40倍希釈で効くのであれば、それでいいのでは?と、私は思います。(ただし、使用液量については、基準を超えないこと、というのは原則です。)
また、ドローン(無人航空機)の適用がない農薬においても、「みかん」や「かんきつ」の適用があるなら、「散布」する方法は、自由なのです。手散布でもSSでも、またはドローンでも構わないのです。たとえば、1000倍希釈で200~300Lを「散布」という適用のある農薬があったとしましょう。これをドローンで1000倍希釈、50L散布しても、法律違反ではありません。基準より少ない量を撒いているだけです。
これは、いわゆる「農薬の節約」や「減農薬」なのですから、常識的に考えて問題ないと私には思えます。しかし、農水省の見解としては、ドローンだろうが何だろうが、「基準を外れた使い方は、すべて悪い」との一点張りです。まるで、現場の悩みに寄り添うというより、他の人(業界)に寄り添っているような言い方ですね。皆さんはどう思いますか?
もちろん農薬というのは危険な化学物質であることが多いですから、消費者や散布する人、または周辺環境にとっての安全な使い方というのは最重要なことであることは言うまでもありません。ただ、ドローン防除という新しい技術に対して、法律や、農薬の登録が遅れているのですから、私たちはいかにして、法令遵守しつつ、新しい技術を柔軟に取り入れていくか、ということに頭を使わなければなりませんね。
ドローンで現実的に使えない農薬と、登録問題
ドローンによる防除で、みかん・かんきつでよく使う農薬について言えば、おそらく唯一「マシン油」がドローンでは、利用できません。利用できないというより、ドローンで撒いても意味が無いのです。それは、害虫を完全に被覆してしまうほどの散布量が必要だからです。同じ理由で、フーモンやムシラップなどの被膜により窒息死させる農薬(気門封鎖剤)は、ドローンでは無意味です。
それから、たとえばクレフノンやホワイトコートについては、ドローンのアトマイザー(液滴を飛散させる回転部品)の消耗を早めてしまうことが予想され、一般的には散布業者さんは、その散布を嫌がります。また「日焼け防止」になるほどの量を散布できないので、やはりこれも基本は手散布ということになるかと思います。
それから、展着剤についても今後の試験・検討が必要です。展着剤は、通常希釈倍数でのドローンでの使用は可能です。一般的には使用方法は「散布」と書いてあるだけだからです。
ただ通常の展着剤は、ドローンで使用すると薬液の粘度が上がってしまい、ミストの粒径(液滴サイズ)が想定よりもかなり大きくなってしまう場合が多いです。液滴サイズが大きいと言うことは、水滴が重くなりますから拡散性が落ちることになり、たとえば葉裏や樹冠内部への付着が悪くなる可能性が高いです。ひどい場合には、樹の表面(樹冠部、および上部)にしかあまり掛からない、ということが想定されるわけです。
そのため、アビオンEやアプローチBIや、スカッシュ、または展着剤としてのマシン油乳剤などは、機械の機能、能力に合わせて使用します。大きい機体であり、アトマイザーの能力が高ければ、標準倍率で問題ないようですが、小さな機体や飛散能力の低いアトマイザーでは、かなり薄くするか、または使用しない方が良いでしょう。ただ、ドライバーやまくぴかのような、濡れ性を上げたり、伸展性を高める展着剤については、そのような場合でも利用価値があるかも知れません。
また、ドローンに適用のある農薬で、カイガラムシに登録のあるものがまだ少ないことも問題だと思っています。現状では、モベントフロアブルのカイガラムシ類と、ダントツ水溶剤のコナカイガラムシ類だけとなっていますから、ちょっと不安があります。
なお、コルト顆粒水和剤は、通常倍率での散布では「カイガラムシ類、アカマルカイガラムシ」に登録があります。なぜドローンによる高濃度散布の場合に、この登録が無いのか、メーカーに聞きましたところコストの問題で適用申請していないようだ、との回答でした。そして「多分、カイガラムシも死ぬだろうけど。。。」と言っていました。幸い、アブラムシ類には適用がありますから、ついでにカイガラムシにも効いてくれることを期待しましょう!笑
(このように、メーカーサイドに余計なコストが掛かるので、農薬登録が進まないという現状があり、農水省さんには、ぜひより良い登録のあり方を考えてもらいたいなと思ったりしています。)
また、みかん・かんきつのカイガラムシでよく使われている、トランスフォームフロアブル、アルバリン顆粒水溶剤(スタークル顆粒水溶剤)、モスピラン(水溶剤、顆粒水溶剤、SL液剤)、アクタラ顆粒水溶剤などは、浸透移行性の高い薬剤ですから、ドローンでの高濃度散布の実用性はあると思います。ぜひ早く無人航空機の登録を進めていただければ良いなと思いますね。
アプロード水和剤もカイガラムシでよく使われていますが、こちらは浸透移行性が謳われていないので、ドローンでの高濃度散布での効果が未知数ですが、やはり今後の登録が望まれます。
また、深刻な被害をもたらすカメムシについても、現在ではダントツ水溶剤とアドマイヤーフロアブルだけとなっていますから、他の薬剤も登録が望まれます。みかん・かんきつで人気のあるテルスターフロアブルは、ビワには無人航空機(ドローン)の登録がありますから、おそらく今後かんきつでも登録がされるのではないかと期待されます。
また、アグロスリン水和剤、アディオン乳剤も、無人航空機での登録が進むと、カメムシ対策の選択肢が増えて良いですね。
それから、ゴマダラカミキリも問題です。ドローンでの防除は一定程度有効ですが、完全に防ぎきれるものではありません。やはり定期的に見回りして早期発見が大切です。また、リスクの高い園地では、手散布になりますがモスピラン顆粒水溶剤の高濃度での主幹・株元散布は、ぜひ実施した方が良いでしょう。
他にも登録が望まれる農薬がありますが、いずれにしても、現在みかん・かんきつに登録があれば、通常希釈倍数であれば、どんな方法であれ「散布」は問題ないわけですから、ドローンで散布しても問題はありません。ただ、使用液量についてはできるだけ、基準に近い量で散布しなければ、効果が出ないことが想定されます。ドローンをお持ちで、チャレンジングな方は、試してみられたらどうでしょうか?
ドローン用途向け葉面散布剤(液肥)
そして、今後の課題としては、ドローンによる高濃度散布に使える葉面散布剤の選択肢が増える必要があると思います。農薬と混用できることが理想ですが、これは、薬液の濃度が著しく高くなるため、葉焼けのリスクを高めることになります。また葉面散布剤の効果メカニズム上、高濃度・少量の散布で、本当に液肥としての効果があるのかについても、今後の検証が必要なことになります。
サンビオティックでも、すこしずつそのテストを進めておりますが、非常にパターンが多く、また検証しにくい内容となりますので、数年では済まない長期間・高難易度の検証作業になりそうです。
そういう事になりますので、しばらくはドローンにてサンビオティック資材の散布を実施される方は、申し訳ありませんが自己責任でのテストをお願いいたします。また、もしその散布の結果を情報提供していただけると、非常に助かります。
以上、ご参考になれば幸いです。
