植物のストレス耐性を高める(塩害、塩類障害、乾燥)
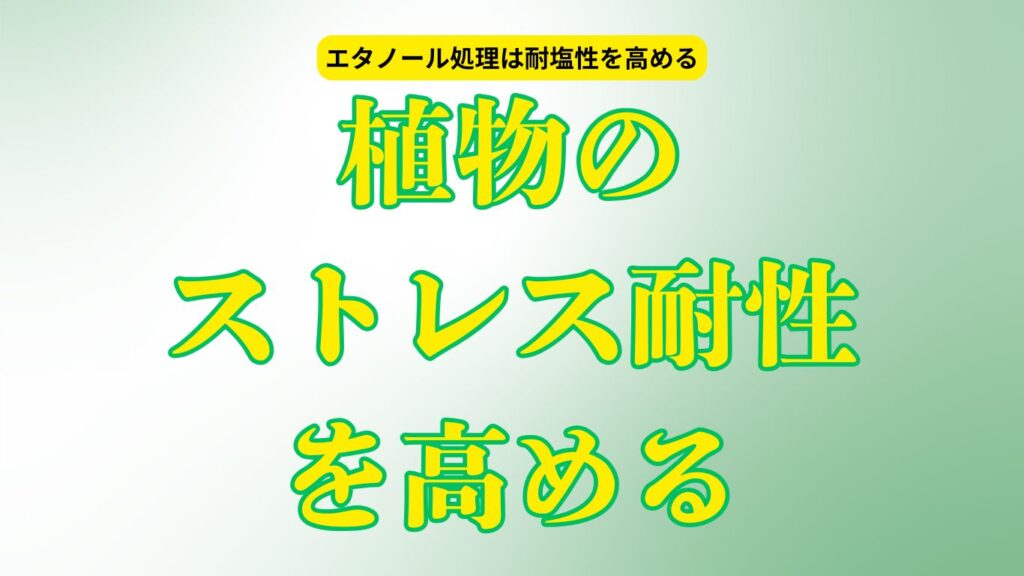
海水による塩害(塩類障害)を改善する方法があるか?
以前、お客様から塩害のご相談メールがありました。
この方は、ハウスなどで肥料分が溜まって起こる塩類障害ではなく、まさに「海水」がかかる畑で、「海側の畑の一部がうまく育たない」、というお悩みでした。今回は、ここに観賞用の花を植えたいという事でのお問い合わせです。これに関連して、エタノールと、酢酸の使い方、また自家製のアルコールやストチューのつくり方まで、アドバイスさせていただきました。
塩害、塩類障害にお悩みの方や、乾燥・高温対策、などにお役に立てるかもしれませんので、ご紹介いたします。
(お客様からのご質問)
塩害対策の件でアドバイスをいただきたくご連絡させていただいております。海が近いため、時より海水の水しぶきが飛んでくる部分で、塩害が発生し、生育が悪いところがあります。
春は花畑にしたいとおもっっています。塩害を抑えていきたいため、イーオス(酢酸)の散布はどうかと思っています。球根の植え付けは11〜12月に行うのですが、酢酸を散布するとしたらいつ頃がいいのでしょうか?
ご教授のほど、よろしくお願い致します。
(回答)
海水による塩害の基本的な対処(除塩)
海水による塩害は、主に塩化ナトリウムによる害です。つまり、塩素イオンとナトリウムイオン(以下「イオン」の表記を省略します。)を除去することがまず重要な対策となります。塩素は比較的容易に水に溶けて流れていく性質がありますから、あまり問題になりません。一方でナトリウムは、土壌に吸着されていて、水を流すだけではすぐに流れていってくれません。そのため、一般的な対処法として、硫酸カルシウム(石膏、硫酸石灰)を施用します。これにより、土壌に吸着されたナトリウムが、カルシウムに置き換わり、ナトリウムが流亡、溶脱しやすくなります。硫酸カルシウム(石膏、硫酸石灰)は、100~200kg/10a程度使用するのが標準量です。炭酸カルシウム(炭カル)でも良いですが、硫酸カルシウムの方が、除塩効果は優れています。
硫酸カルシウム以外にも、転炉石灰などでも除塩ができるようです。詳しくは転炉石灰を調べてみて下さい。
上記の様に石灰資材を施用した後、塩分のない「真水」を十分に潅水して、塩類濃度を薄めることが大切な処置となります。水量は50~100トン/10a程度は最低でも必要でしょう。露地であれば、しばらく雨に当てておくだけでも良いです。
除塩後の生育不良、発根不良には菌力アップが有効
また、除塩作業を行っても、ナトリウムが多く残ってしまい、ナトリウム過剰害で発根不良となるケースは多いです。ナトリウム過剰では、根が傷む(塩漬け状態)であることと、マグネシウムや加里などの要素欠乏が生じやすくなることが問題です。これを改善するため、菌力アップの使用と、マグネシウムや加里の液肥を、潅水や葉面散布するなどして、バランスをとることも重要と思います。
上記の通り、塩害による発根不良には、菌力アップが適しています。海水による塩害だけでなく、ハウスなどの土壌では、肥料成分が過剰に残り塩害となるケースも多いです。土壌分析でいうと、EC値が高すぎるためにおこる塩類障害という減少です。
このような場合は、菌力アップを発根期に週に1回程度潅水すると、植物の耐塩性が高まり、生育が良くなることは、干拓地などの塩害の試験でも実証済みです。例えば、塩トマト(潮トマト)はあえて、塩類濃度の高い土壌で栽培するものですが、どうしても生育が不良となります。そこで菌力アップを使用すると、味を落とさずに、収量を上げていくことが可能となります。
エタノールが植物の耐塩性を高める(理化学研究所)
さて、ここからは、すこし塩害についての最新の情報を元に、お話を進めます。まず、理化学研究所の研究により、植物の耐塩性が「エタノール」によって向上するという事が判明し、発表されました。
・エタノールが植物の耐塩性を高めることを発見
https://www.jst.go.jp/pr/announce/20170703/index.html
理由は、エタノールが活性酸素(ROS)の除去に関する遺伝子を活性化するためのようです。また、類似する研究として、酢酸により、植物の乾燥・高温耐性た高まることが発見されています。
・エタノール・酢酸処理で塩害・乾燥に強く 農作物のストレス耐性を高める
https://www.jst.go.jp/seika/bt2019-08.html
非常に面白い発見だと思います。酢酸は、ジャスモン酸というストレス耐性を高める植物ホルモンを誘発するようです。
ここまで読んだ読者の皆さん、「何だ、塩害や乾燥の話か」と短絡的に早とちりしないで下さいね!
これは、とても大切な事だと思うのです。
植物にとっての「活性酸素」は、人に例えると「痛み」
実は、植物にとって外的なストレスは、たくさんあります。塩ストレスや乾燥ストレス以外にも、高温、低温、光(日光)、病害虫、機械的傷害(外傷)なども、日常的に植物がさらされているストレスです。このようなストレスに遭遇したとき、植物の体内では、まず「活性酸素」が発生するんです。活性酸素は、ある種のシグナルとして働いていて、自分自身がストレスにさらされていて、身を守る働きをしないといけないことを全身の組織や細胞に伝えているのです。
このことは、私たち人に例えると、活性酸素→痛み、と考えるとわかりやすいかも知れません。私たちも、さまざまなストレスに遭遇すると肉体的な痛みや、精神的な痛みを感じますね。そのことによって、自分自身が傷ついたことを知りますし、自分の身を守らなければという咄嗟(とっさ)の反応に繋がります。私たちに、もしも「痛み」がなければ、きっとすぐに危険な行為をして、死んでしまうことでしょう。
このようなメカニズムと、まったく同じ事が植物でも行われているんですね。ストレスを全身に伝えるために、活性酸素が作られ、放出される。それをきっかけとして、防御物質を作ったり、細胞壁を硬くしたり、損傷した組織を再生したりするための反応ができるんです。活性酸素は、DNAに作用しストレス応答遺伝子のスイッチをオンにします。すると、ストレスに対抗し、自分自身を守るための様々なホルモンが生成されます。ジャスモン酸や、サリチル酸、エチレン、アブシジン酸などがその代表的なストレス対抗ホルモンです。まったく、凄い仕組みですよね!!
ところがです。当然ながら、良いことばかりではありません。この活性酸素が過剰に作られることが、植物の細胞、組織そのものを傷つけるという、まさに痛い代償があるのです。
植物は、体内に活性酸素が過剰になると、途端に細胞を傷めて、生きていくことができなくなります。つまり、ストレスによる細胞への直接的な被害を回避するためには、いかに活性酸素を除去する能力を高めるか?が大変重要なストレス耐性能力になると言うことです。
ここで、先ほどのエタノールや酢酸を思い出して欲しいのです。
この話は、「エタノールや酢酸が、塩ストレスや乾燥ストレスを軽減するのに役立つ」というだけの話ではないと言うことです。「エタノールや酢酸で、ストレスに対抗するためのメカニズムが発動した!」という発見が大切なんです!つまり、これらは、塩ストレスや乾燥ストレスだけでなく、様々なストレスに対抗するために役立つ可能性が高い!という事なのです。
どうでしょうか?面白いですよね!!
考えてみると、有機農家などが昔から作って愛用いる「ストチュー」という資材は、酢酸と焼酎(エタノール)が主成分となっています。やはり、植物のストレス耐性を高めるためには、非常によい作用があるのだと思います。
酢酸資材「イーオス」の活用で、ストレス耐性を高める
さて、酢酸(食酢)の場合は、弊社の15%高酸度食酢の「イーオス」をお勧めいたします。一般に流通している食酢の3倍以上の酢酸濃度があり、経済的です。
草花は、植付け後、1か月もすると、旺盛に発根している時期と思います。そのため、イーオスは、植付けの1ヵ月後から、100〜150倍希釈で、10日おき程度に散布・潅水してみてはいかがでしょうか。葉が大きくなってくるころからは、暖かくもなりますので、葉焼けの心配もあります。今回は、観賞用ですので、3月くらいからは300倍希釈で、散布・潅水してください。つぼみが上がり始めるころまでやるとよいと思います。
次に、エタノールですが、これは弊社ではお取り扱いがございません。amazonやモノタロウなどで、「エチルアルコール」で調べていただきますと、90%程度のものが一斗缶で販売されているようです。先述の耐塩性向上の試験では、エタノール0.3%溶液で効果があったとのことのようですので、エタノール製剤は、3000倍希釈で使用すると良いと思います。
※ただし、エタノール製剤については、私自身も植物に試したことがありませんので、ご自分で情報等ご確認の上、ご自身の責任でお願いいたします。m(__)m
手作りエタノール(アルコール)の作り方と使い方
ただ、エタノール製剤は価格が高いですので、家庭菜園や小規模農家の方にはハードルが高いですね。それならば、手作りされてはいかがでしょうか?作るところも楽しんだらいいですね!
あくまでも、参考としてですが、下にレシピを書いてみます。
・水(1晩汲み置き→カルキ抜き) 1500cc
・砂糖(白砂糖、黒砂糖、赤糖、なんでもよい) 400g
・パン酵母(ドライイースト) 1袋(3g)
・コーソゴールド 50g(市販の液肥や、飲用に適さないもの)
これを、2Lのペットボトルに入れ、良く溶かし、最後に満タンまで水をいれて、蓋をかぶせておきます。(密封すると破裂します。空気が抜ける程度にしてください。)
酵母がアルコール発酵をして、泡(CO2)がどんどん発生します。アルコールが作られている証拠です。美味しそうな良いにおいがします。泡がある程度収まるまで、2〜3週間暖かい所に置いておくと、出来上がります。(泡の発生がピークを越えたら良いです。)良いにおいに寄せられてコバエが寄ってきますので、虫のいないところや、虫が来ても気にならないところが良いと思います。布などをかぶせて、ハエが産卵しないように注意してください。
なお、発酵が不十分ですと、砂糖をまくことになりますから、病害虫を誘引する可能性があります。十分に発酵し、泡の発生が穏やかになるころまで置くと良いでしょう。
なお、コーソゴールド(市販の液肥)を混ぜるのは、「農業用」と明確にするためで、酒税法の適用を受けないためです。「飲用できるもの」を作ると、酒税法違反となりますから、私の立場上、このブログではこのように書かなければなりません。
このように、手作りで発酵させて植物に与えている篤農家様は、意外に多いです。安く、そして効果がありますね。〇〇酵素など買うよりも、かなりお安く、簡単に作ることができます。(より「酵素」を増やしたい場合は、「天恵緑汁」のつくり方を参考にしてみてください。)
これを、100〜300倍希釈で散布・潅水することで、植物の耐塩性を高めることができる可能性があると思います。発酵程度が軽いものほど、希釈倍率は薄くします。病害虫を誘引するリスクを軽減する目的も踏まえて、酢酸と混ぜて、散布・潅水されて良いと思います。
ストチューの作り方と使い方
ちなみに、先述の手作り資材「ストチュー」を作る場合は、下記の配合率を参考にしてください。
(市販の焼酎を使う場合)
高酸度食酢「イーオス」 15%
純正木酢液 40%
焼酎(25度) 45%
(手作りアルコール発酵液を使う場合)
高酸度食酢「イーオス」 20%
手作りアルコール 80%
こちらは、どちらも潅水、葉面散布ともに使用できます。通常100〜300倍希釈で使用しますが、薄めからお試しください。このストチューに、野草やニンニクやタバスコなどを混ぜたり、付け込んだりするかたもいらっしゃいます。問題はないと思いますが、効果のほどはわかりません。それから、腐れる可能性がありますので、あまり作り置きはしないほうが良いと思います。
また、酢酸には高濃度であると殺菌作用がありますから、菌力アップとは混合せず、別々にやるようにして下さい。
以上、面白いストレスの話でした。ご参考になれば幸いです。
このブログ記事の投稿者プロフィール

株式会社大地のいのちの代表取締役社長 生田と申します。農業資材や有機肥料などの開発を通じて、また有用な情報の提供を通じて、生産者の皆様に喜んでいただければと思っています。農業技術専門家の立場から、サンビオティック農業の解説や、土づくり、栽培に関する事、日々の想いや感じたことをつづっていきたいと思います。


